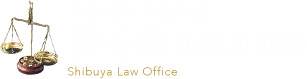■特別縁故者とは
相続が開始されると、被相続人(亡くなられた方)の遺産は、被相続人の生前の遺言がない限り、相続人が引き継ぐのが通常です。相続人は、民法に定められている法定相続人として、被相続人の配偶者・子・両親・兄弟姉妹といった人が挙げられます。これらの相続人が遺産を分け合って、相続することになります。
しかし、相続人ではない人が遺産を引き継ぐことができる制度があります。それが、特別縁故者の制度です。特別縁故者とは、相続人ではないものの、生前の被相続人と特別な関係にあった人のことを指し、被相続人の遺言がない場合であっても、遺産を引き継ぐことができます。
●特別縁故者とはどのような人のことをいうのか
そもそも、特別縁故者が遺産を受け取ることができるのは、どのような場合なのでしょうか。
それは、被相続人に法定相続人がいないケースです。先ほど確認した通り、法定相続人には、被相続人の配偶者や子どもなどが含まれています。法定相続人がいないケースというのは、例えば、そもそも配偶者がいない場合や、両親がすでに亡くなっている場合、法定相続人に当たる人の全員が相続放棄をしている場合などにより、相続人が不存在であることが考えられます。
次に、上記のような特別縁故者が遺産を受け取れる場合に該当するとして、どのような人が特別縁故者であるといえるのでしょうか。
民法の958条の2において、「被相続人と生計を同じくしていた者」、「被相続人の療養看護に努めた者」、「その他被相続人と特別の縁故があった者」が特別縁故者に該当するとされています。例えば、生計を同じくしていた者であれば、内縁の夫や妻、事実上の養子や養親がこれに該当します。また、療養看護に努めた者には、実際に、被相続人を献身的に介護していた人などがこれに該当します。その他被相続人と特別の縁故があった者については、ほかの例と同等レベルで、被相続人と密接な関係を築いていた人が該当するといえるでしょう。
●特別縁故者の申立てについて
特別縁故者であれば直ちに相続財産を受け取ることができるわけではなく、一定の手続きを経る必要があります。具体的には、特別縁故者自身が家庭裁判所に対して、特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行います。その場合、家庭裁判所は、その人が特別縁故者に該当しているかどうかの判断を行い、該当していると判断されれば、財産分与をどのくらいの割合で行うかについて決定します。
その前提として、まずは相続財産管理人の選任を申し立てて、相続財産管理人を選任した後、相続財産管理人の申立てにより家庭裁判所が相続人捜索の公告を行います。相続人の不存在が確定すれば、いよいよ特別縁故者に対する相続財産分与の申立てを行う、という流れです。
●相続に関するご相談は当事務所まで
渋谷徹法律事務所は、文京区をはじめとする都内を中心に、全国各地の相続問題に関するご相談を承っております。特別縁故者の制度についてより詳しく知りたい方や、特別縁故者の申立ての方法などについてご不安がある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
特別縁故者になれるのはどんな人?申立ての流れも併せて解説
渋谷徹法律事務所が提供する基礎知識
-

別居中の生活費は配偶者...
「離婚を考え、配偶者と別居状態にあるが、生活費が心もとない。請求することは可能だろうか。」 別居期間中...
-

相続の流れ
相続手続きの大まかな流れは次の通りです。 まず、被相続人が死亡した(相続開始)後、7日以内に死亡届を...
-

敷金償却とは
マンションやアパートの一室を賃貸する際に、敷金を支払うことがあります。 これはほとんど日本における賃...
-

特別縁故者になれるのは...
■特別縁故者とは 相続が開始されると、被相続人(亡くなられた方)の遺産は、被相続人の生前の遺言がない限...
-

遺産、財産の使い込み
相続トラブルの中でも多いのが、相続開始(被相続人が亡くなる時)前後で相続人の一人が遺産・財産を使い込ん...
-

退去時の原状回復におい...
退去時の原状回復においてトラブルが起きることは避けたいですが、時には予想よりも高額の原状回復費用を求...
-

裁判離婚
離婚の最終形とも言えるのが、「裁判離婚」。つまり、裁判所に離婚の訴えを提起し、離婚を成立させてもらう制...
-

遺言書の種類
遺言書には①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があり、遺言者はこのいずれかの方法で遺...
-

賃料の回収
賃料を支払わない入居者に対して契約解除を求めようとしても、賃借人が1か月程度家賃を滞納したぐらいでは...